その痛み、諦めないで。あなたの膝には、まだやれることがたくさんあります。
「変形性膝関節症です」と診断され、これからどうしたらいいのだろうと、途方に暮れていませんか? 「お薬を出しておきますね」「少し様子を見ましょう」 そう言われただけでは、きっと不安な気持ちが残ってしまいますよね。こんにちは、整形外科医の堀口です。
実は、変形性膝関節症の治療は、病院で受けるものだけがすべてではありません。むしろ、治療の本当の主役は、患者さん、あなた自身なんです。あなたの「治りたい」という気持ちと日々の小さな努力が、治療の効果を何倍にも高めてくれます。
今回は、手術以外の治療法、いわゆる「保存療法」について、ご自身の力でできることも含めて、希望の光となるようなお話をしていきたいと思います。
変形性膝関節症治療のキホン|「保存療法」とは何か?
病気の治療には、大きく分けて「手術をする治療」と「手術をしない治療」の2つの道があります。この「手術をしない治療」のすべてを、私たちは「保存療法」と呼んでいます。
保存療法は、いわば自分の力で膝の機能を大切に保ち、痛みと上手に付き合っていくための治療法です。具体的には、「運動療法」「薬物療法」「物理療法」など、様々なアプローチがあります。
私たちの治療のゴールは、単に痛みを取ることだけではありません。その先にある、「痛みが出る前の、あなたらしい生活を取り戻すこと」。これこそが、私とあなたが共に目指すゴールです。
実際の診察で、いきなり手術をおすすめすることは滅多にありません。ほとんどすべての方が、まずはこの保存療法から、回復への第一歩を踏み出します。さあ、一緒に始めましょう。
治療の絶対的エース!「リハビリテーション(運動療法)」
数ある保存療法の中で、私が「これだけは絶対に続けてほしい!」と情熱を持ってお伝えしているのが、リハビリテーション、つまり運動療法です。これは、治療の選択肢の中でもまさに「絶対的エース」と言える存在です。
なぜ運動が重要?膝を支える“頼れる筋肉”を育てよう
膝の変形が進んでしまう大きな原因の一つに、歩く時の「膝のグラつき」があります。これを専門的には「スラスト」と呼びますが、イメージとしては、軸がブレてしまったタイヤのようなもの。タイヤの軸がブレていると、車体がガタガタ揺れて、他の部品にも負担がかかりますよね。それと同じことが、あなたの膝でも起こっているのです。このグラつきが、膝の軟骨に余計なダメージを与え、変形を進行させてしまいます。
では、どうすればこのグラつきを抑えられるのか?
答えはシンプルです。膝の周りの筋肉を鍛え、天然のサポーターとして育てること。筋肉が膝をガシッと支えてくれれば、安定性が増し、軟骨への負担を減らすことができるのです。
特に重要なのが、太ももの内側にある**「内側広筋(ないそくこうきん)」という筋肉です。これは、膝を守るための最重要ボディガード**。ぜひ、この筋肉の名前だけでも覚えておいてください。
そして、硬くなりがちなお尻や太ももの裏の筋肉は、優しくストレッチして動きを滑らかにしてあげましょう。
自宅でできる最強の「筋力トレーニング」
「運動と言われても、何をしたら…」
ご安心ください。私が診療で必ずお伝えしている、誰でもできて、とても効果的なトレーニングを一つ、ご紹介します。
【ペットボトル潰しトレーニング】
- 床に足を伸ばして座ります。
- 痛い方の膝の裏に、蓋をした空の500mlペットボトルを置きます。
- そのペットボトルを、「ギューッ!」と真下に押し潰すように、太ももに力を入れます。
- 2〜3秒キープしたら、力をスッと抜きます。
- これを「潰す」「抜く」「潰す」と、歩くようなリズムで繰り返します。
ポイントは、思い切り潰すこと。たったこれだけです。
「何回やればいいですか?」とよく聞かれますが、この運動はやりすぎて悪くなることはありません。むしろ、やればやるほどあなたの膝は安定していきます。
私の患者さんで、みるみる痛みが改善していく方は、1日300回くらいを目標に頑張ってくれています。「300回!?」と驚くかもしれませんが、1回あたりは数秒です。100回でも5分から10分程度。朝の情報番組を見ながら、食後に必ず、といったように、生活の中に組み込んで「習慣」にしてしまうのが成功の秘訣です。
「気が向いたらやる」というスタンスだと、残念ながらなかなか痛みは改善しません。毎日の歯磨きのように、あなたの膝のための新しい習慣を、今日から始めてみませんか?
膝の動きを滑らかにする「ストレッチ」
筋トレとセットで行いたいのが、ストレッチです。特に、お尻や太ももの裏の筋肉が硬くなっていると、膝への負担が増えてしまいます。
一番簡単なのは、体育の授業で誰もがやったことのある**「長座体前屈」**。床に足を伸ばして座り、ゆっくりと体を前に倒す、あの運動です。膝をできるだけ曲げず、つま先を掴むようにすると、ふくらはぎまで気持ちよく伸ばせますよ。
もし、「あぐらをかくのが辛い」と感じるなら、それはお尻の筋肉が硬くなっているサインかもしれません。あぐらをかくような姿勢で、お尻の筋肉を伸ばすストレッチも効果的です。
リハビリについては、あなたの「もっと知りたい!」という声にお応えして、近いうちに写真や動画を使った、もっと分かりやすい解説記事を準備する予定です。ぜひ、楽しみにお待ちくださいね!
辛い痛みを抑えるサポーター役「薬物療法」
リハビリが主役なら、お薬は**「辛い痛みを和らげ、あなたが前向きにリハビリに取り組むための、頼れるサポーター」**です。決して、薬だけに頼りきりになるべきではありません。
飲み薬(鎮痛薬)の種類と注意点
よく処方される飲み薬には、痛みを抑える「アセトアミノフェン」や、痛みと炎症の両方に効く「NSAIDs(エヌセイズ)」(ロキソニンなどが有名です)があります。
どの薬を選ぶかは、あなたの年齢や体の状態、副作用などを総合的に判断して、私たちが責任を持って調整しますのでご安心ください。
私はいつも患者さんにこうお伝えしています。 「このお薬は、痛みのせいで諦めていたリハビリを『よし、やってみよう!』と思えるようにするためのお守りです。主役であるリハビリを頑張ることが、10年後、20年後のあなたの笑顔につながる一番の近道ですよ」と。
湿布・塗り薬の正しい使い方と効果
湿布や塗り薬は、あなたが使ってみて「気持ちいいな」「楽になるな」と感じるものを選ぶのが一番です。ただし、飲み薬と併用する際には注意が必要なタイプもありますので、必ず医師や薬剤師に相談してくださいね。
膝の潤滑油&クッション役「関節内注射」
ヒアルロン酸注射|膝の動きを滑らかにする
これは、膝関節にとっての**「潤滑油」を補充してあげるような注射です。**軟骨を保護し、膝の動きを滑らかにする効果が期待できます。
ただし、その効果は永久ではありません。私の考えでは、この注射はあくまでリハビリを頑張るためのサポート。最終的には、あなた自身の筋肉で膝を支え、この注射を「卒業」することを一緒に目指していきたいと思っています。
ステロイド注射|強い炎症を抑える“切り札”
痛みが非常に強く、炎症が起きている場合の「切り札」として使うのがステロイド注射です。効果はありますが、繰り返し使用すると逆に関節を傷めてしまうリスクもあります。長期的な視点を大切にしているため、私がこの注射を使うのは、本当に必要な時だけに限定しています。
その他にできること|装具療法・物理療法
他にも、あなたの膝を助ける選択肢はあります。
「物理療法」は、電気や超音波などを使って痛みを和らげるもので、リハビリの効果を高める応援団のような存在です。
「装具療法」は、膝のサポーターや、靴の中に入れる足底板(そくていばん)を使って、外部から膝を安定させる方法です。ご高齢でリハビリが難しい方や、痛みが強くて運動ができない場合に、一時的な助けとしてとても有効です。
また、最近では軟骨を再生させる「再生医療」も進歩していますが、現時点では保険が適用されず高額なのが実情です。これもいずれ詳しくお話しできる記事を準備しています。
まとめ|治療の主役は、あなた自身です
ここまで、手術以外の様々な治療法についてお話ししてきました。
たくさんの選択肢がありますが、最も大切なことはたった一つ。それは、**「あなた自身が、自分の体と向き合い、治すために行動する」**ということです。
私たち医療者は、専門知識と技術で、あなたの隣を走り、全力でサポートする伴走者です。でも、ゴールテープを切るのは、他の誰でもない、あなた自身の足です。
大丈夫。やれることは、本当にたくさんあります。
諦める必要なんて、どこにもありません。一緒に、元気な膝を取り戻していきましょう。
さあ、あなたの回復への旅(航海)を始めましょう。Bon Voyage!
免責事項
本記事は一般的な医療情報の提供を目的としたものであり、個別の診断や治療を保証するものではありません。症状に心当たりがある方は、必ず医療機関にご相談ください。

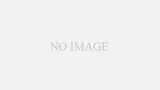
コメント